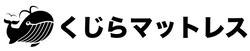センターハードマットレスとは?特徴と種類
センターハード マットレスは、通常のポケットコイルマットレスとは異なり、中央部分のコイルを硬めに設計したタイプです。その名の通り、腰部分に重点的なサポートを提供します。 センターハード マットレスの特徴 腰痛対策に効果的: センターハード構造は、腰部分に適切なサポートを提供するため、腰痛を抑える効果があります。 体型ごとに選びやすい: 仰向きや横向きの寝姿勢に適しているため、幅広い体型に対応できます。 センターハード マットレスの種類 3ゾーン/5ゾーン/7ゾーン: センターハード構造のマットレスは、硬さの調整が異なる3つのゾーンから7つのゾーンまであります。数字が大きくなるほど、身体の部位に合わせて細かく硬さが調整されています。 高反発/ポケットコイル: センターハード構造のマットレスは、主に高反発ウレタンかポケットコイルが使用されています。予算や体圧分散の要件に応じて選ぶことができます。 おすすめのセンターハード マットレス 以下は、センターハード構造のマットレスの中からおすすめの商品です。 くじらマットレス: 60パターンの硬さ調整が可能で、腰痛&肩こり対策に効果的。仰向け・横向きどちらでも寝やすい設計です。 アイリスオーヤマ センターフィットマットレス MAF5: 凹凸構造の高反発マットレスで、腰部分の沈み込みを防ぎます。 タンスのゲン 3ゾーン構造 ポケットコイルマットレス: 腰の沈み込みを防止し、ポケットコイルで体圧分散を向上させています。